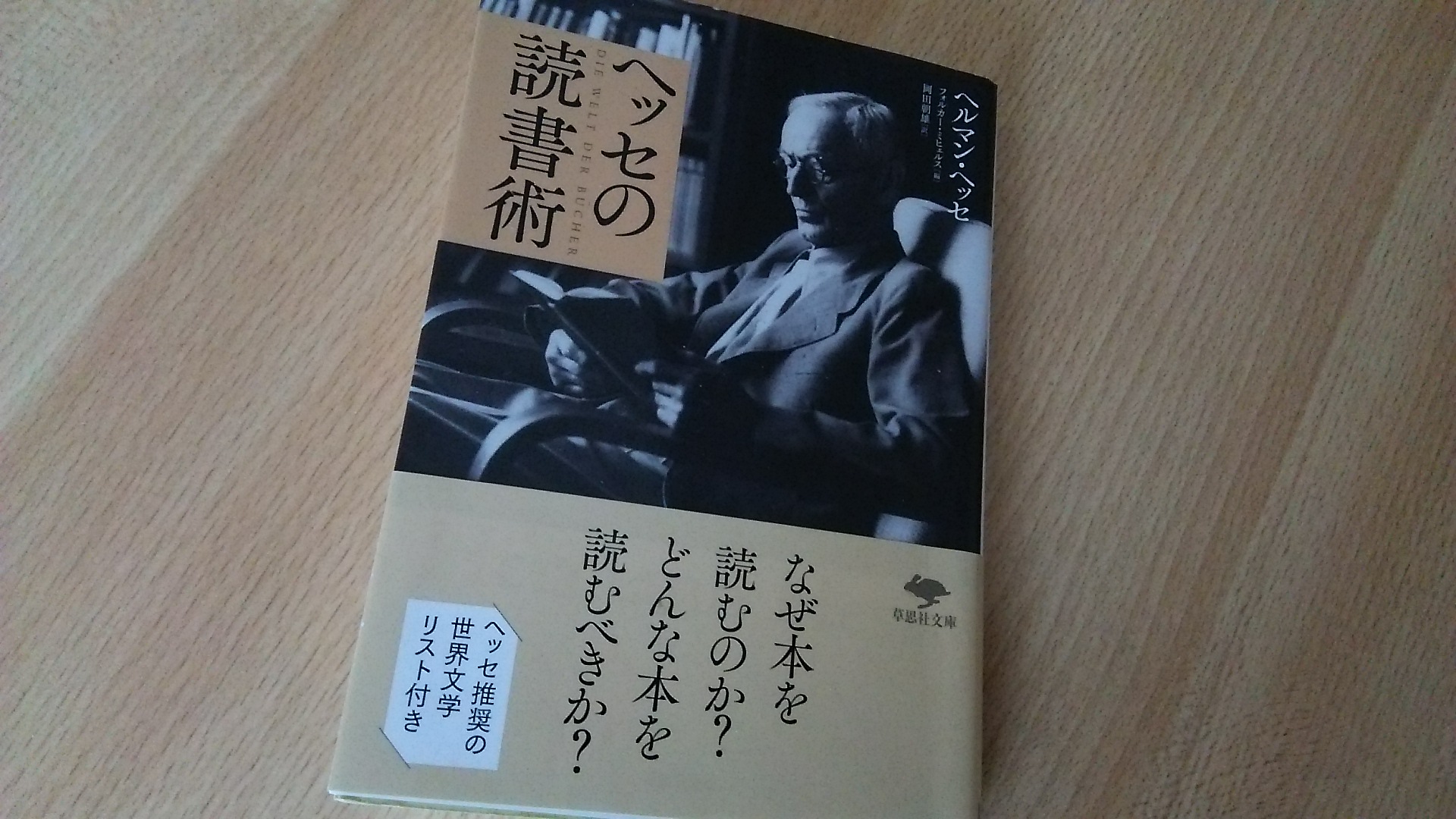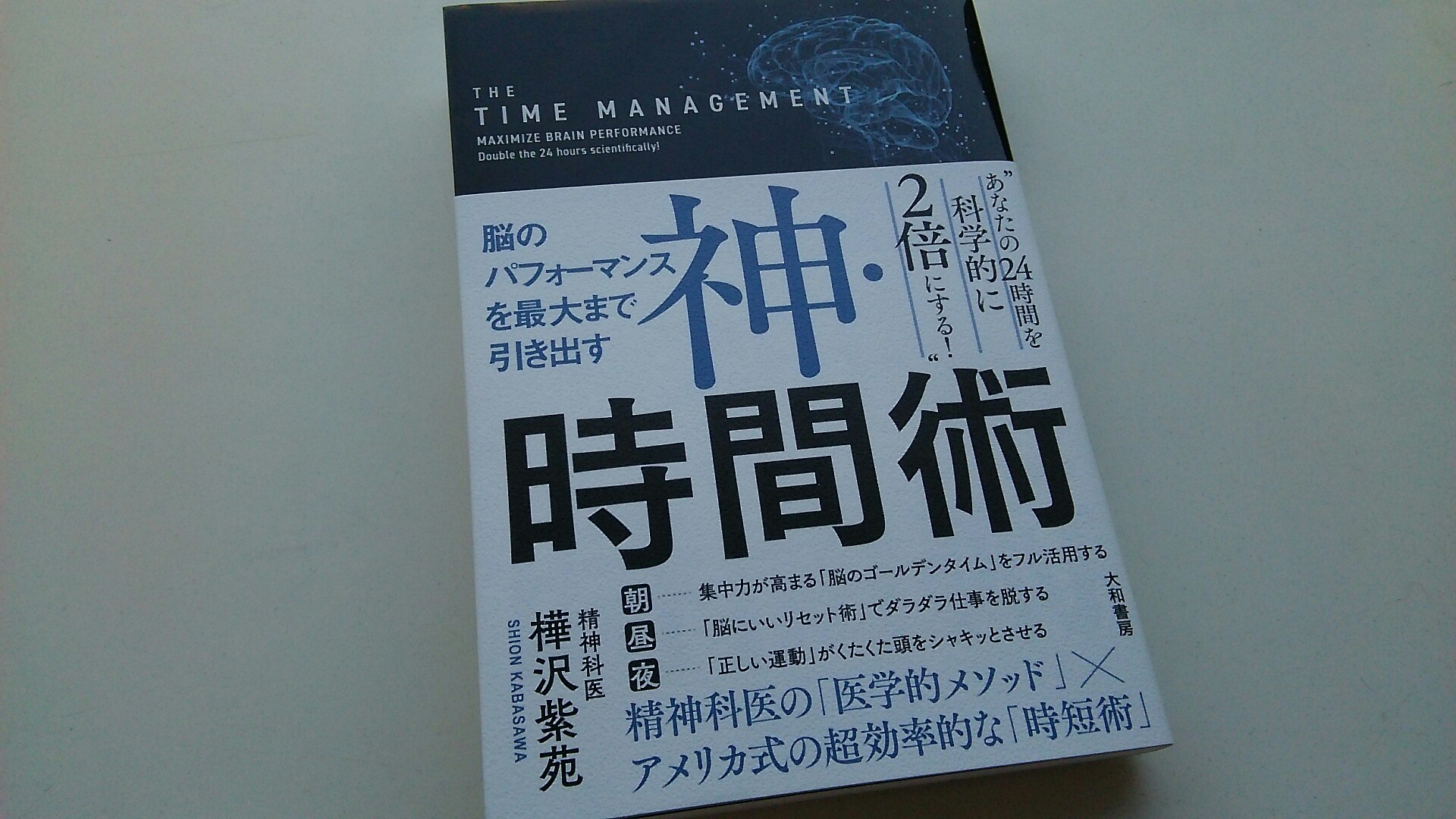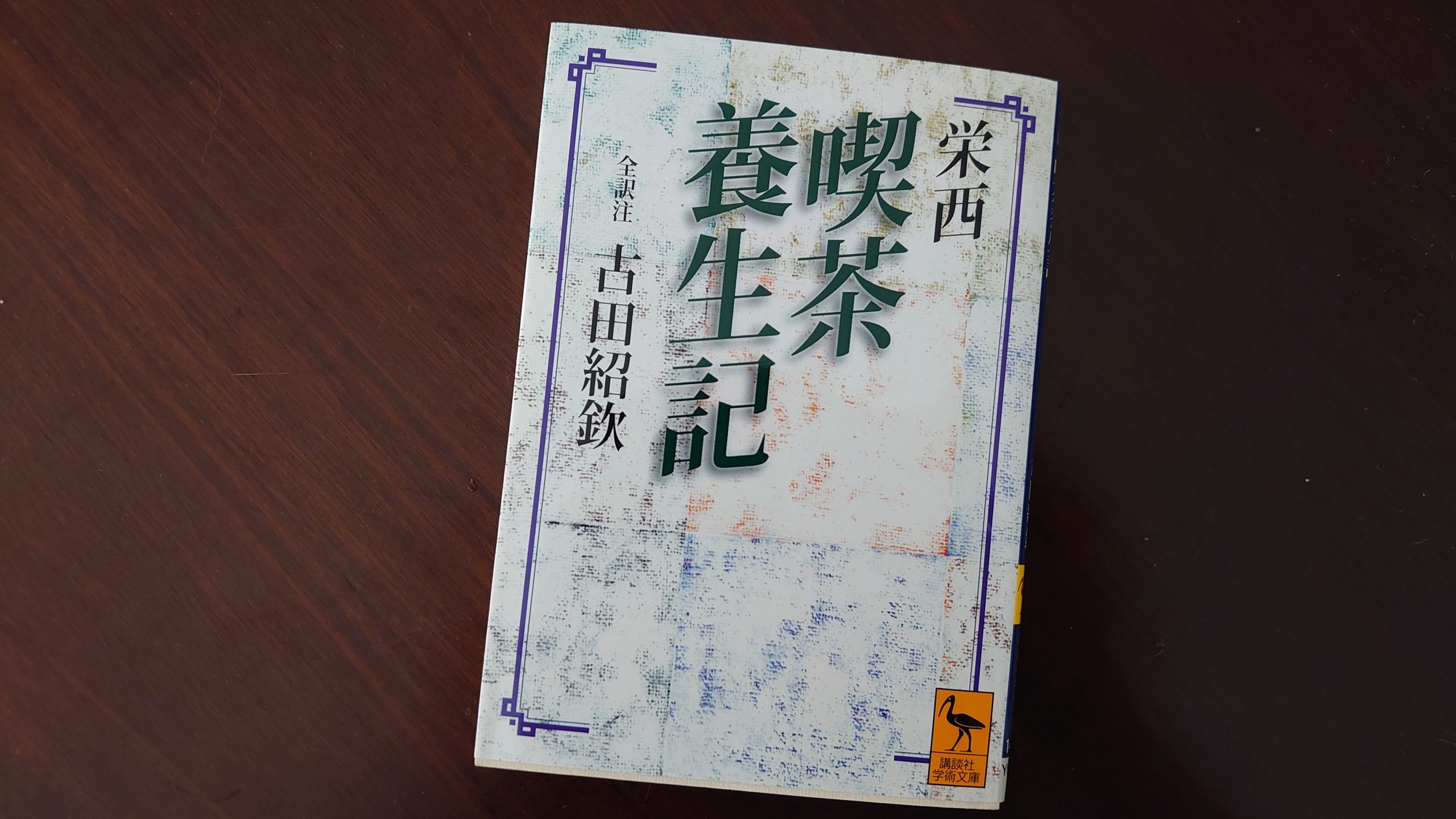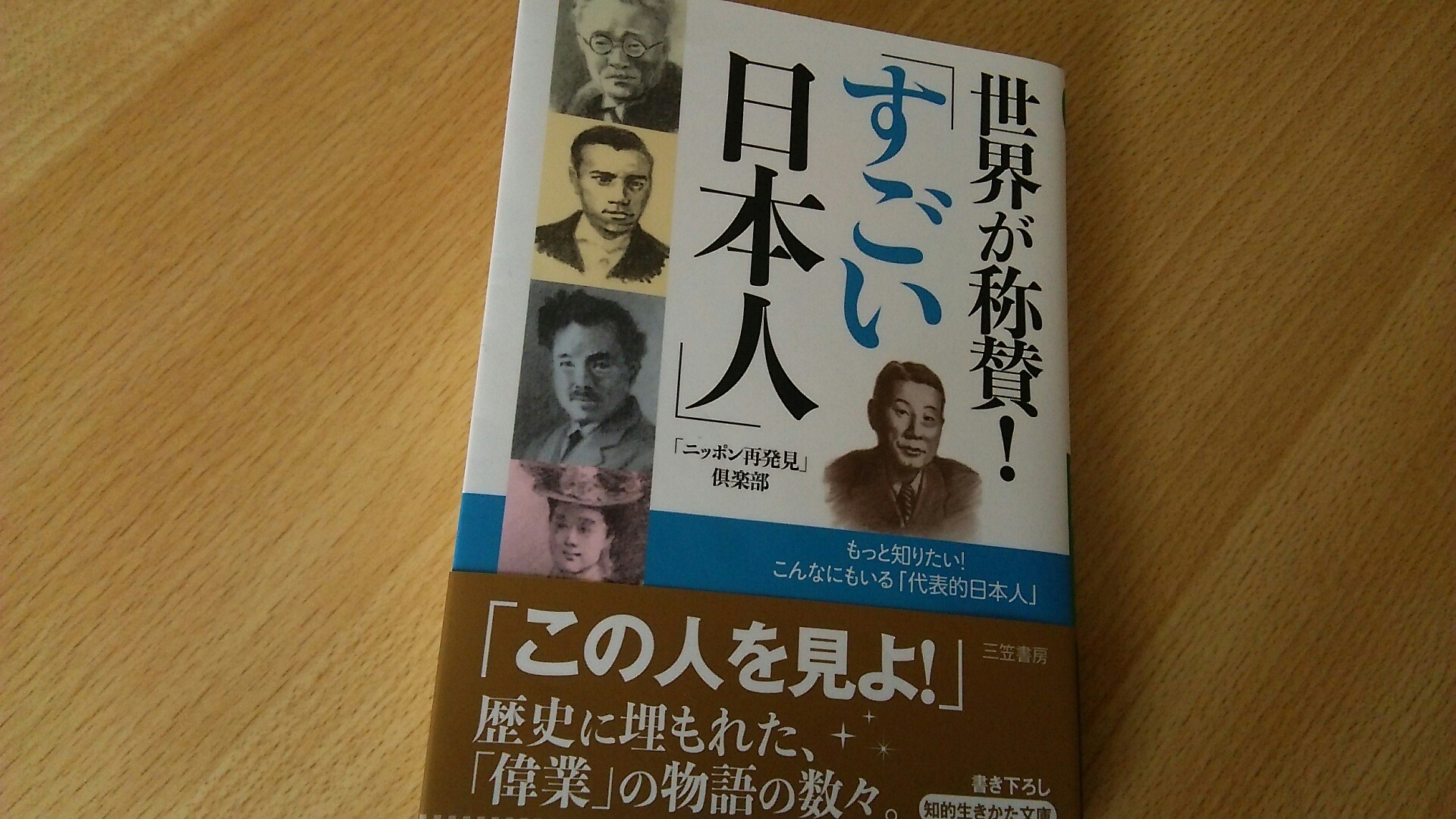民俗学者の宮本常一(1907-1981年)は、「旅の巨人」と呼ばれました。日本各地を歩いた距離は、地球4周分に相当する16万キロ。歩いて、物を見て、考えるというのが「宮本民俗学」の基本になっています。
この基本姿勢は、常一が大阪に出る際、父の善十郎から教えられたものです。常一は、著書「民俗学の旅」の「父」の中で、「出るときに父からいろいろのことを言われた。そしてそれを書いておいて忘れぬようにせよとて私は父のことばを書きとめていった」として、10項目を書いています。その中で、主なものは――。
(1)汽車に乗ったら窓から外をよく見よ、田や畑に何が植えられているか、育ちがいいかわるいか、村の家が大きいか小さいか、瓦屋根か草葺きか、そういうことをよく見ることだ。・・・
(2)村でも町でも新しくたずねていったところはかならず高いところへ上がってみよ、そして方向を知り、目立つものを見よ。・・・
(3)金があったら、その土地の名物や料理は食べておくのがいい。その土地の暮らしの高さがわかるものだ。
(4)時間のゆとりがあったら、できるだけ歩いてみることだ。いろいろのことを教えられる。
(5)~(8)略
(9)自分でよいと思ったことはやってみよ。・・・
(10)人の見のこしたものを見るようにせよ。その中にいつも大事なものがあるはずだ。・・・
こう読んでいくと、常一がこれらの父の言葉を忠実に守り、宮本民俗学の基本に据えたことがわかります。
スポンサードリンク
 |
新品価格 |
![]()
自分の足で歩いて、目で見て、できるだけ多くの1次情報を集める。高いところから見るというのは、物事を俯瞰し、大局をとらえるということでしょう。そこから、自分で事象に関して独自の分析を加える。
「塩の道」「ふるさとの生活」「庶民の発見」「忘れられた日本人」などの名著が生まれた理由がわかります。
上の10項目の主なものを見てもわかりますが、例えば、「わるい」「たずねていった」「ところ」など通常なら漢字にするところで、常一は、ひらがなをたくさん使っています。庶民に沿った視線も感じられます。
これらの格言を頭に描きながら、自分の好きな場所を歩いたら、新しい視点が生まれて、いい旅になるでしょう。