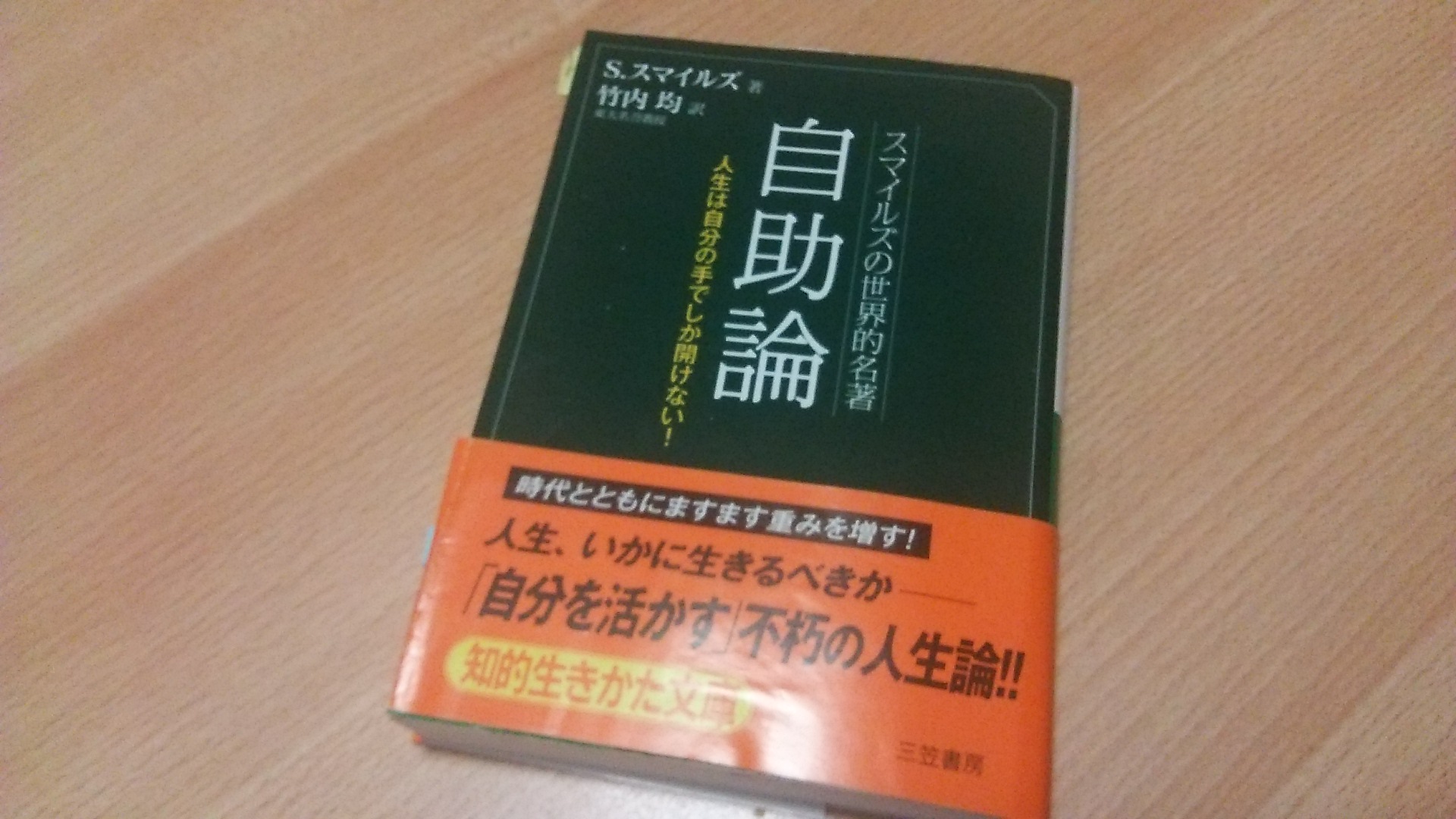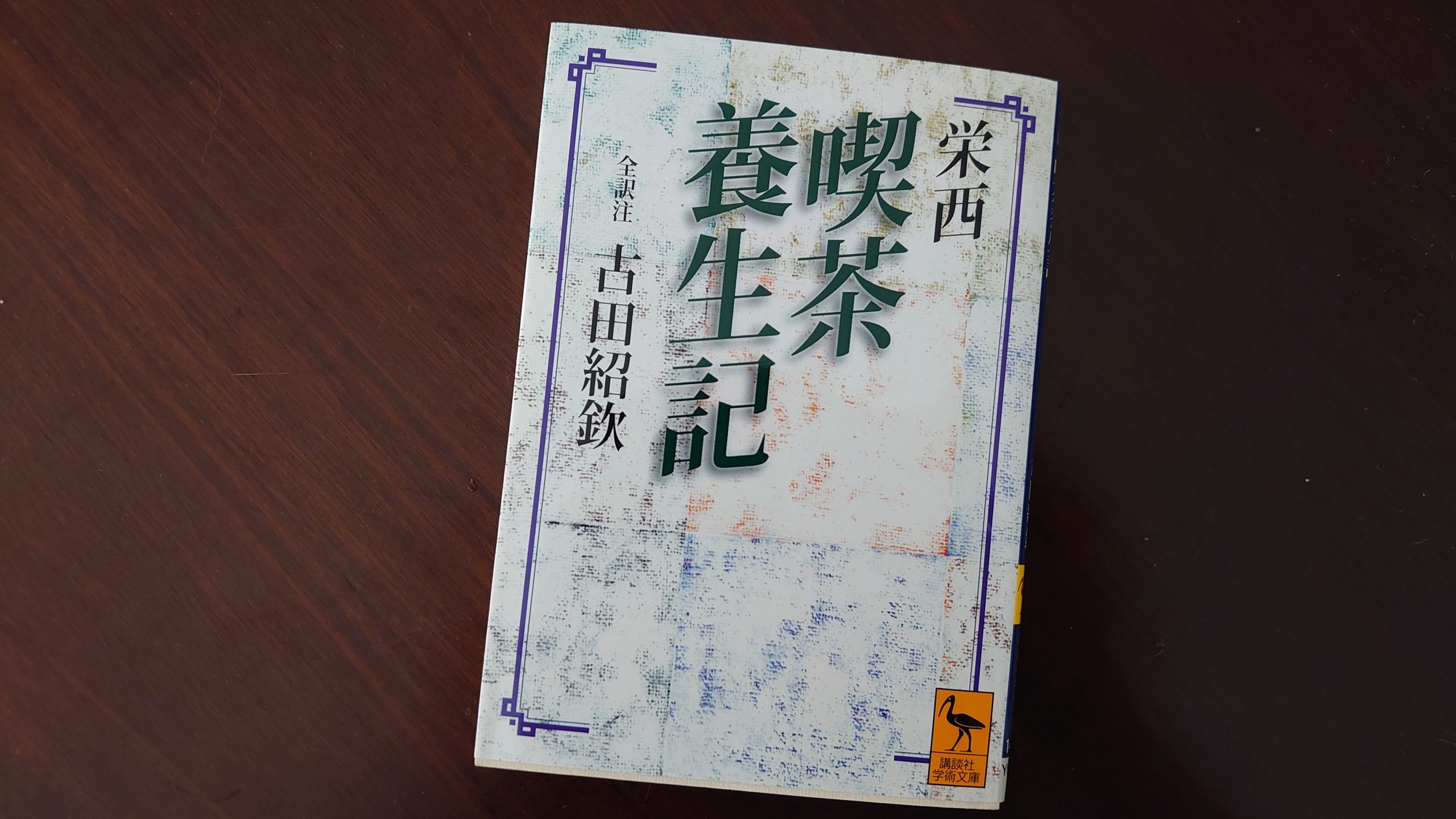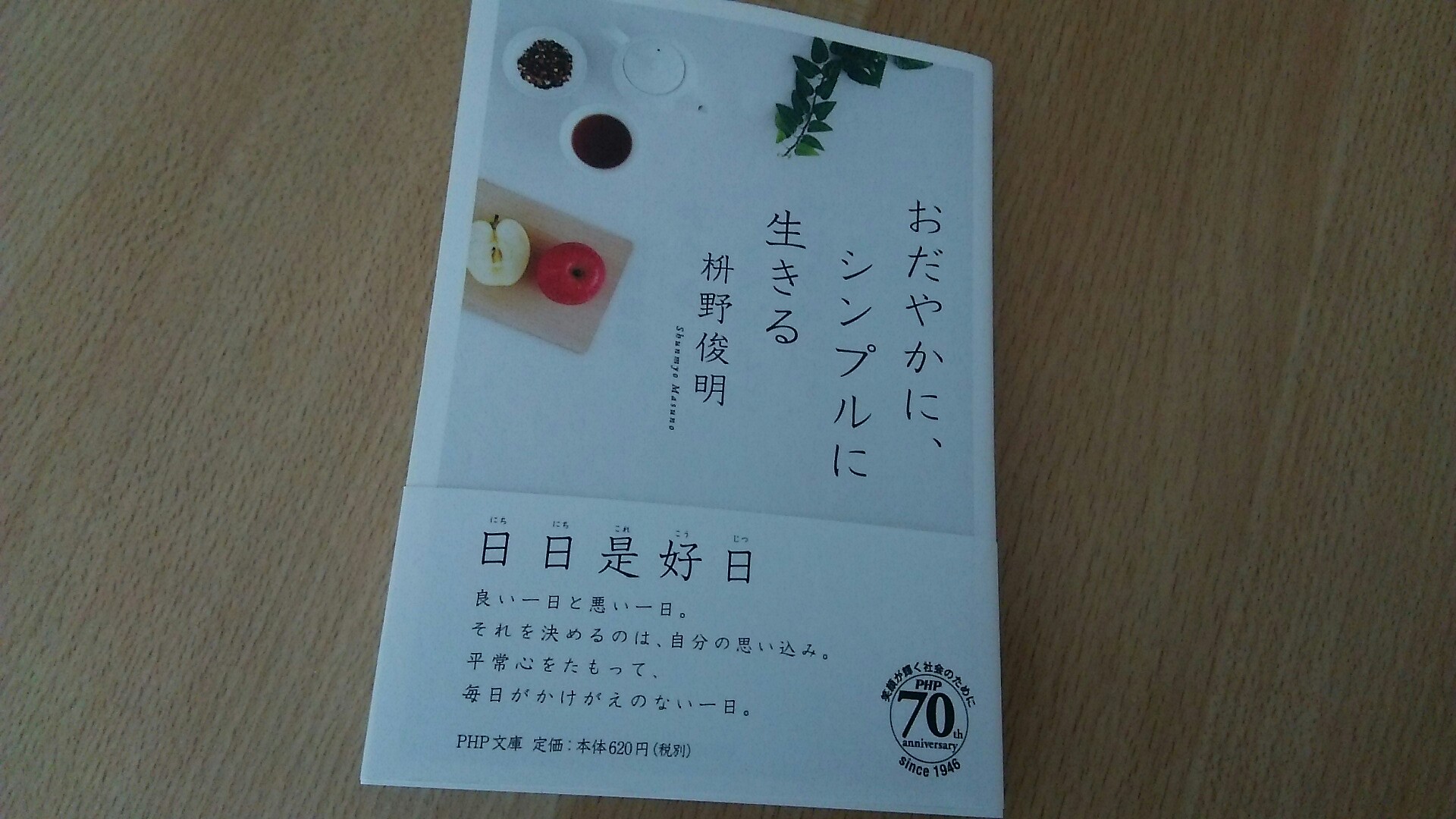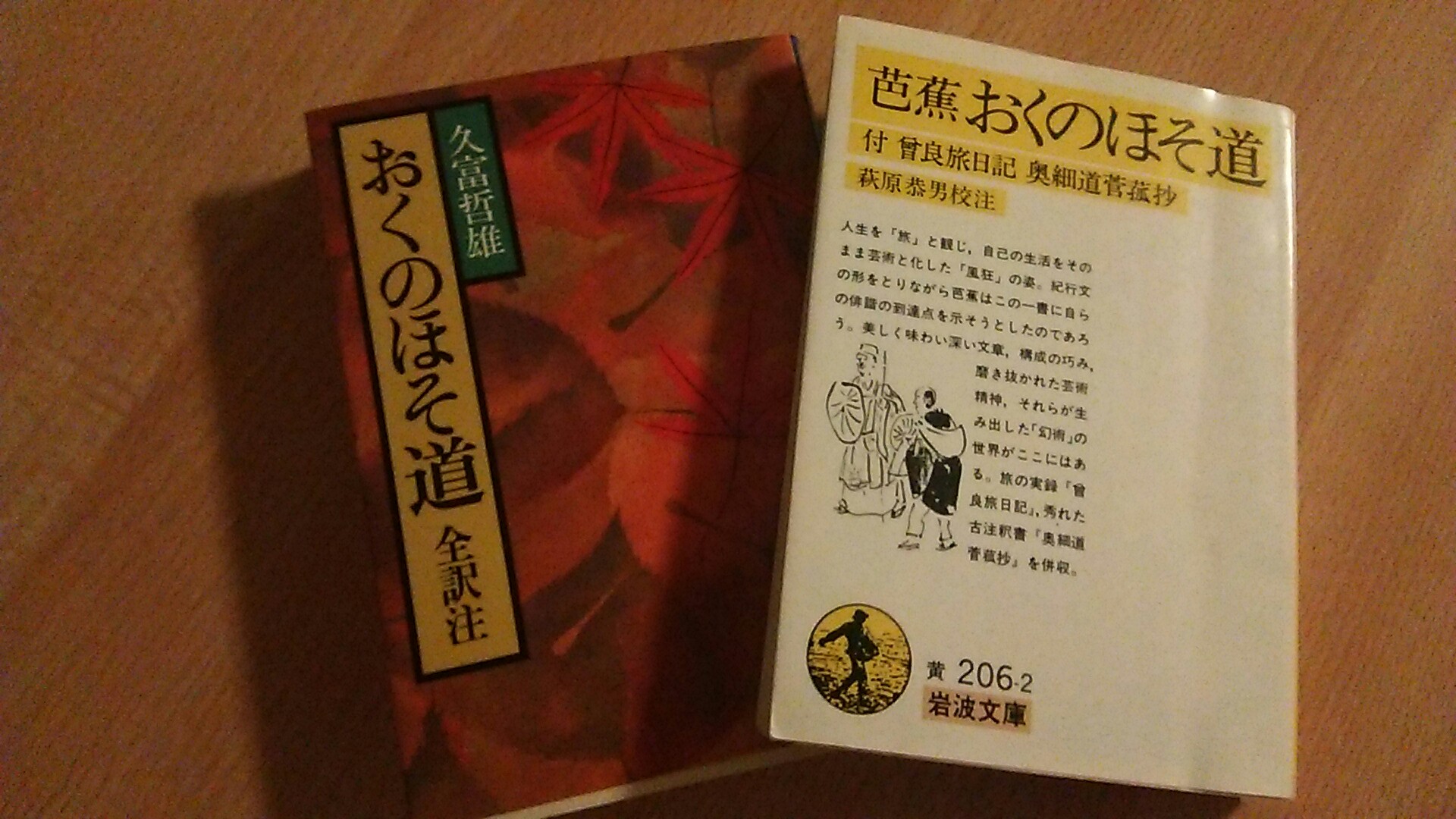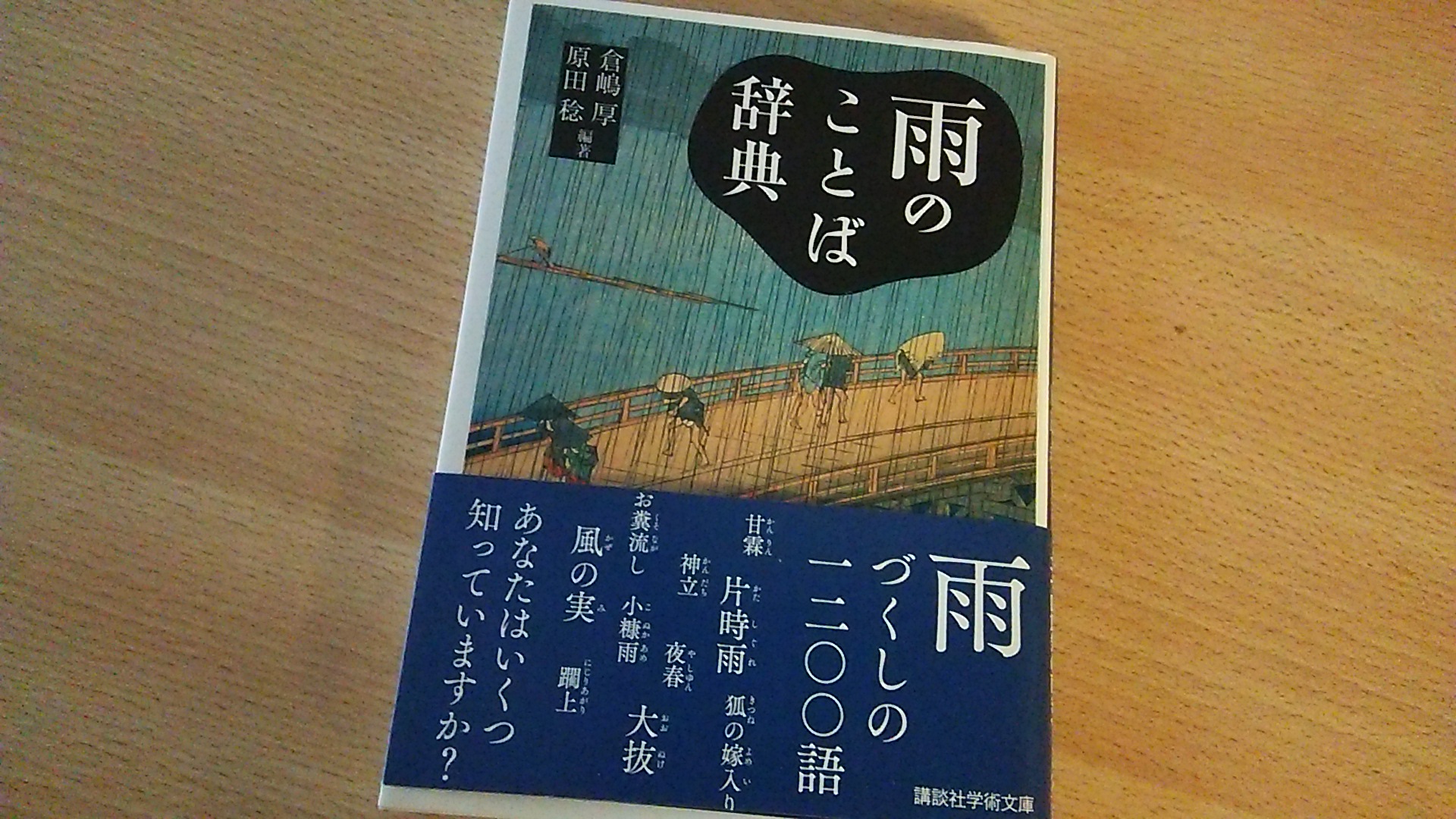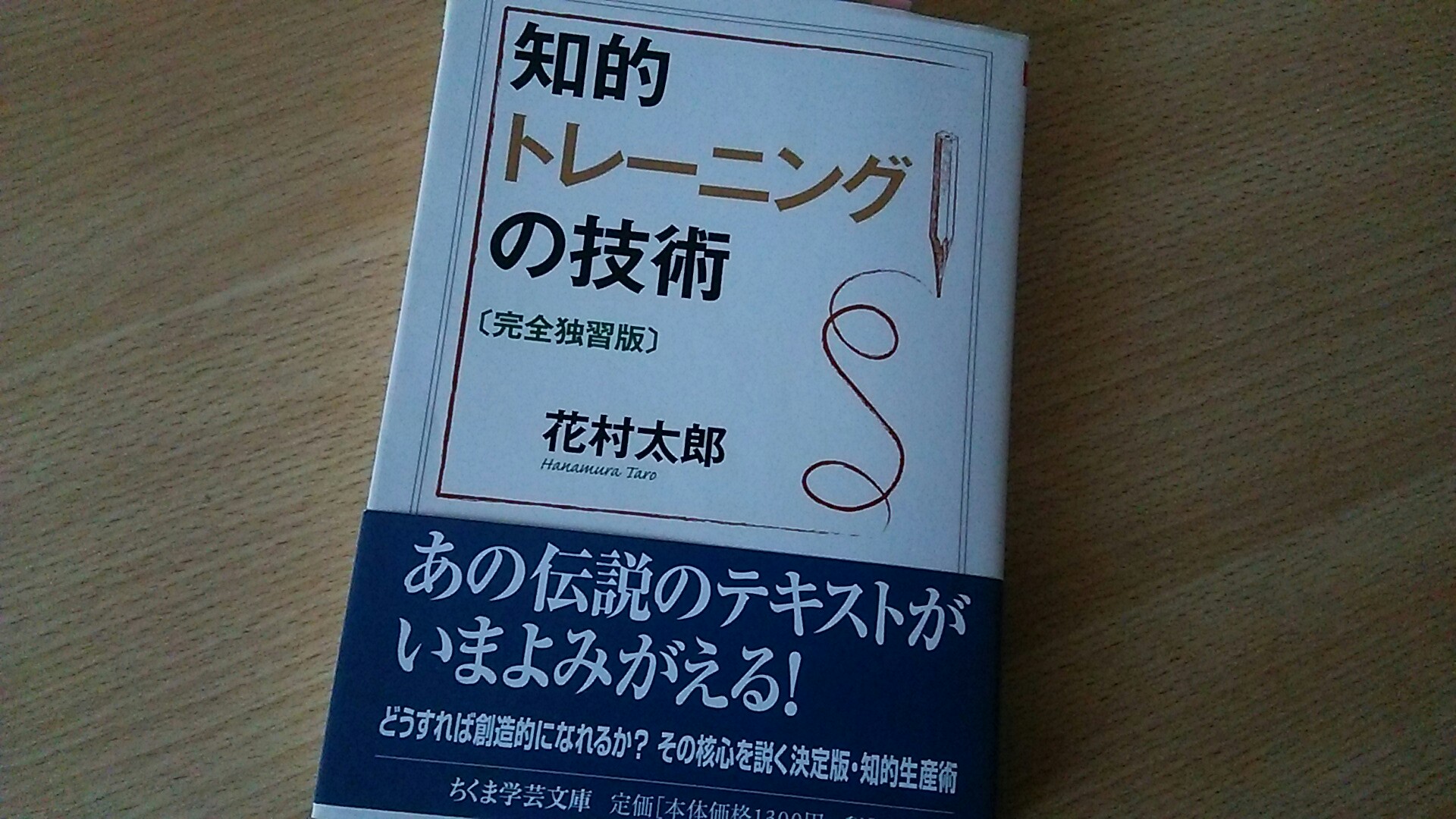地球4周分の16万キロを歩いて日本各地を調査した民俗学者の宮本常一は、10万枚以上の写真を撮ったことでも知られています。「読める写真を撮る」が信条で、昭和という時代の移り変わりを記録しました。
宮本常一が撮影したのは、昭和30年から55年の間です。昭和時代の農村、漁村、山村あるいは東京、大阪の都会の景観や、そこに生きる人々が写真でとらえられています。
著書「宮本常一と写真」にも、たくさんの写真が載っています。故郷の山口県周防大島の茅葺屋根の農家や田畑をはじめ、石垣を背に本を読む少年、カゴを背負って買い物をする少女、行商と赤帽の人々、舟で通学する子供たち、愛知県東栄町御園の花祭りの榊鬼(さかきおに)、東京・信濃町駅前でメーデー会場に向かう人々――など、その時代の様子がわかります。
1枚1枚見ているだけで、語りかけてくるような写真ばかりです。昭和の時代があります。
スポンサードリンク
 |
新品価格 |
![]()
「はっと思った時、おやっと思った時に写真を撮れ」と宮本常一は言ったそうです。この本の中でも、民俗学写真家の須藤功さんが、宮本常一から民俗学の教えを受ける中で、「芸術写真は撮るな、読める写真を撮れ」と繰り返し言われたことを書いています。
歩いて、物を見て、考えるというスタイルの中で、1次情報を大切にしてきたことが、この、写真で時代を記録するという点でもわかります。
もう一度、写真の持つ力を考えてみたいものです。