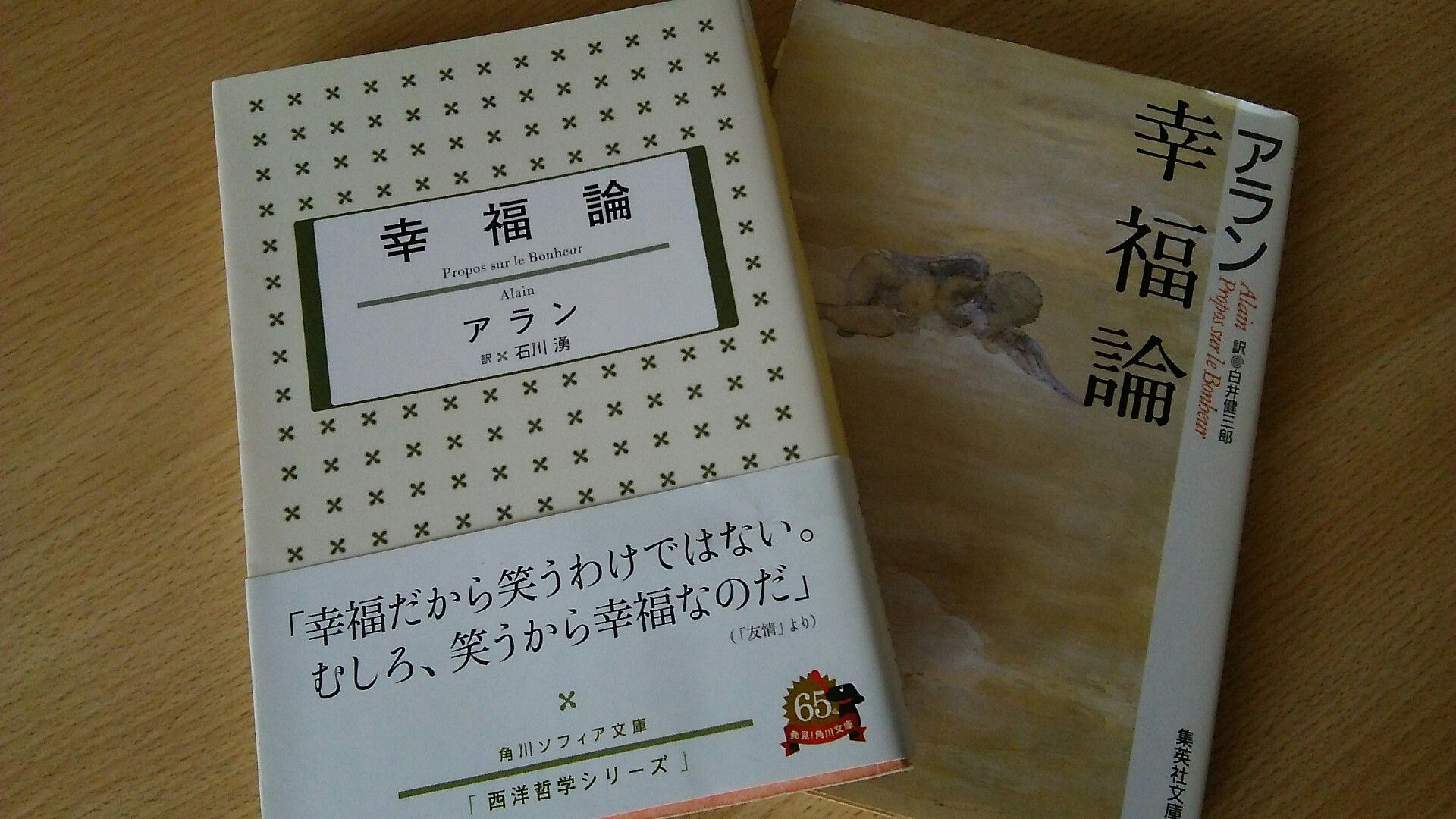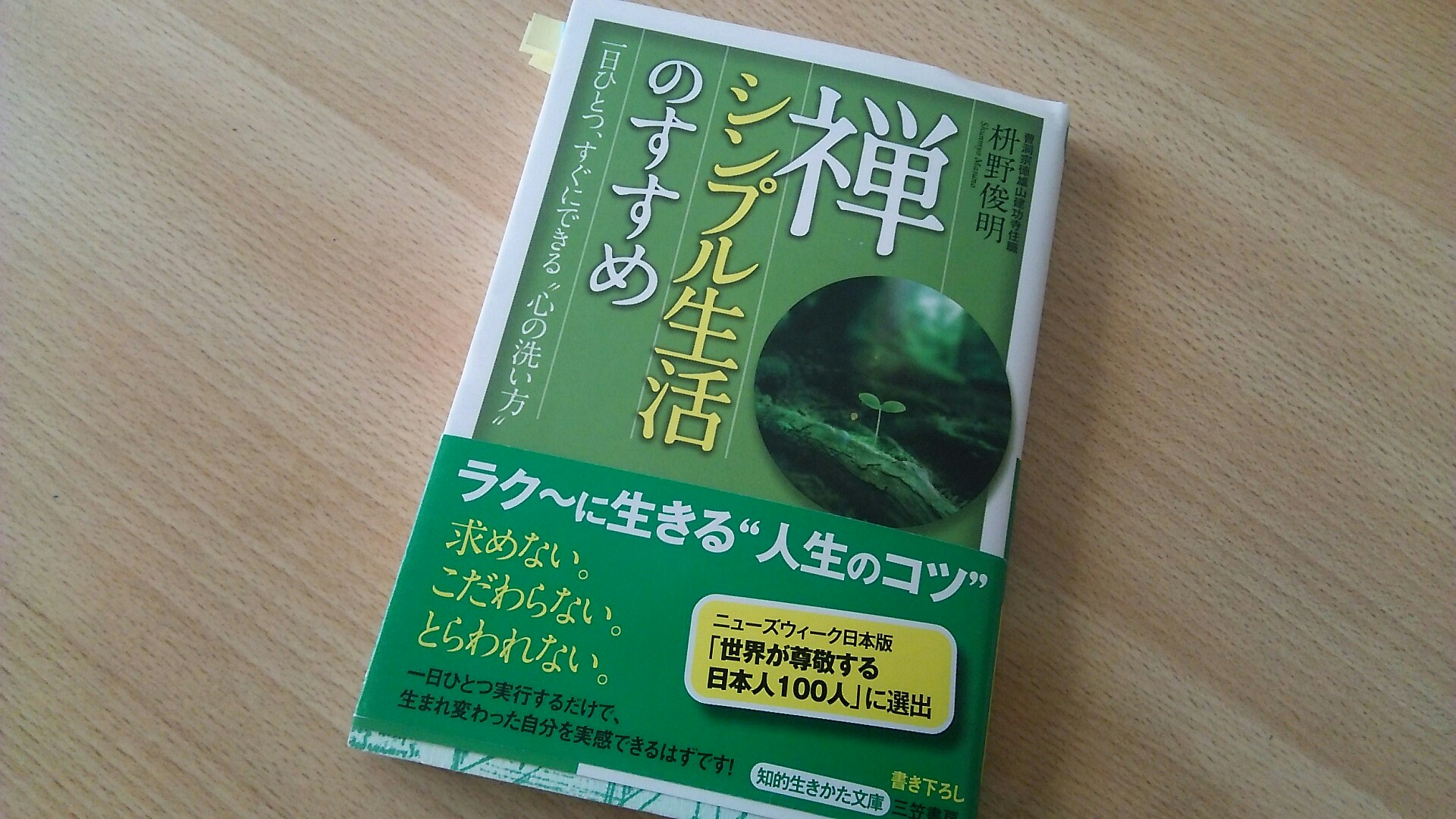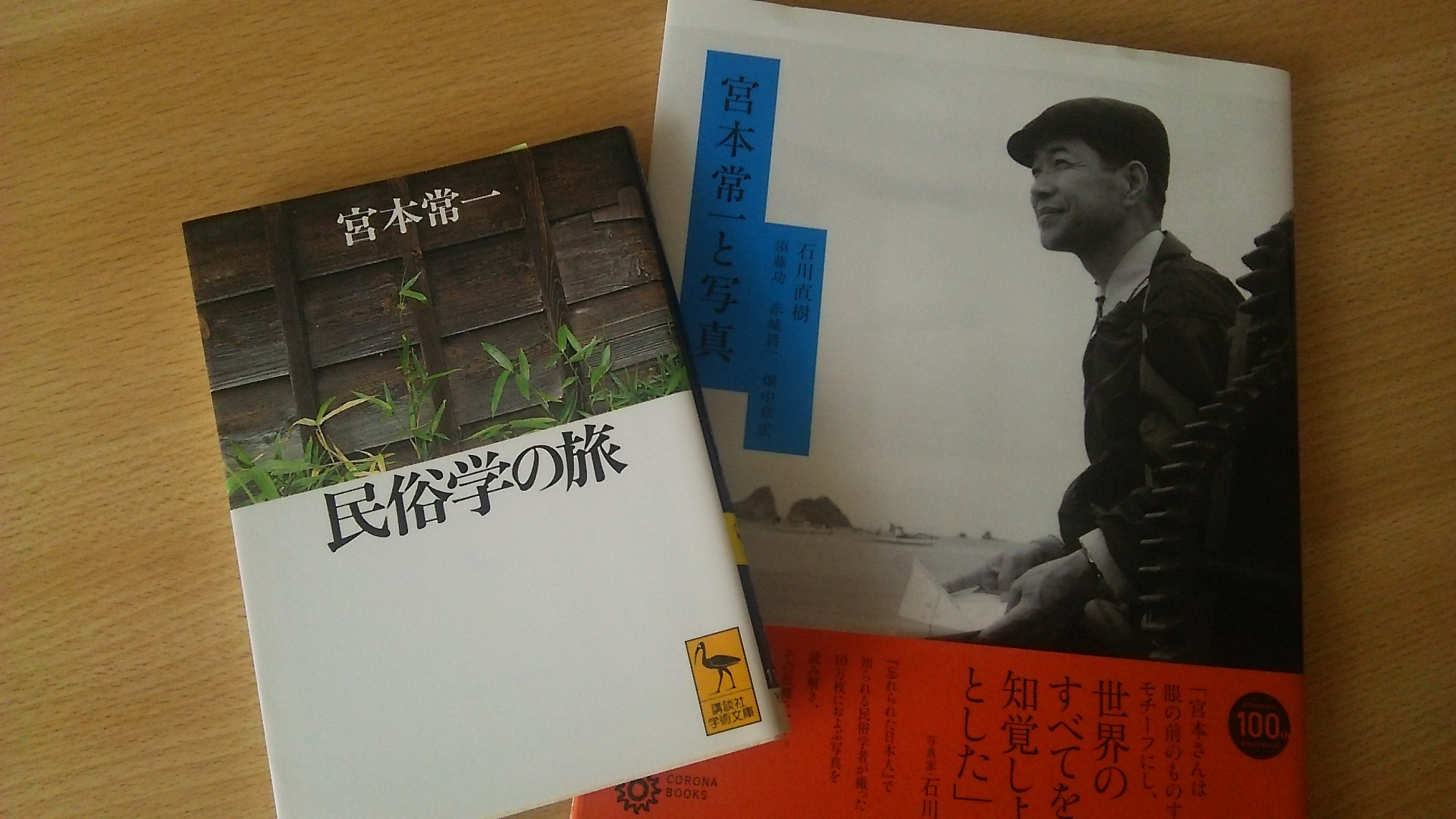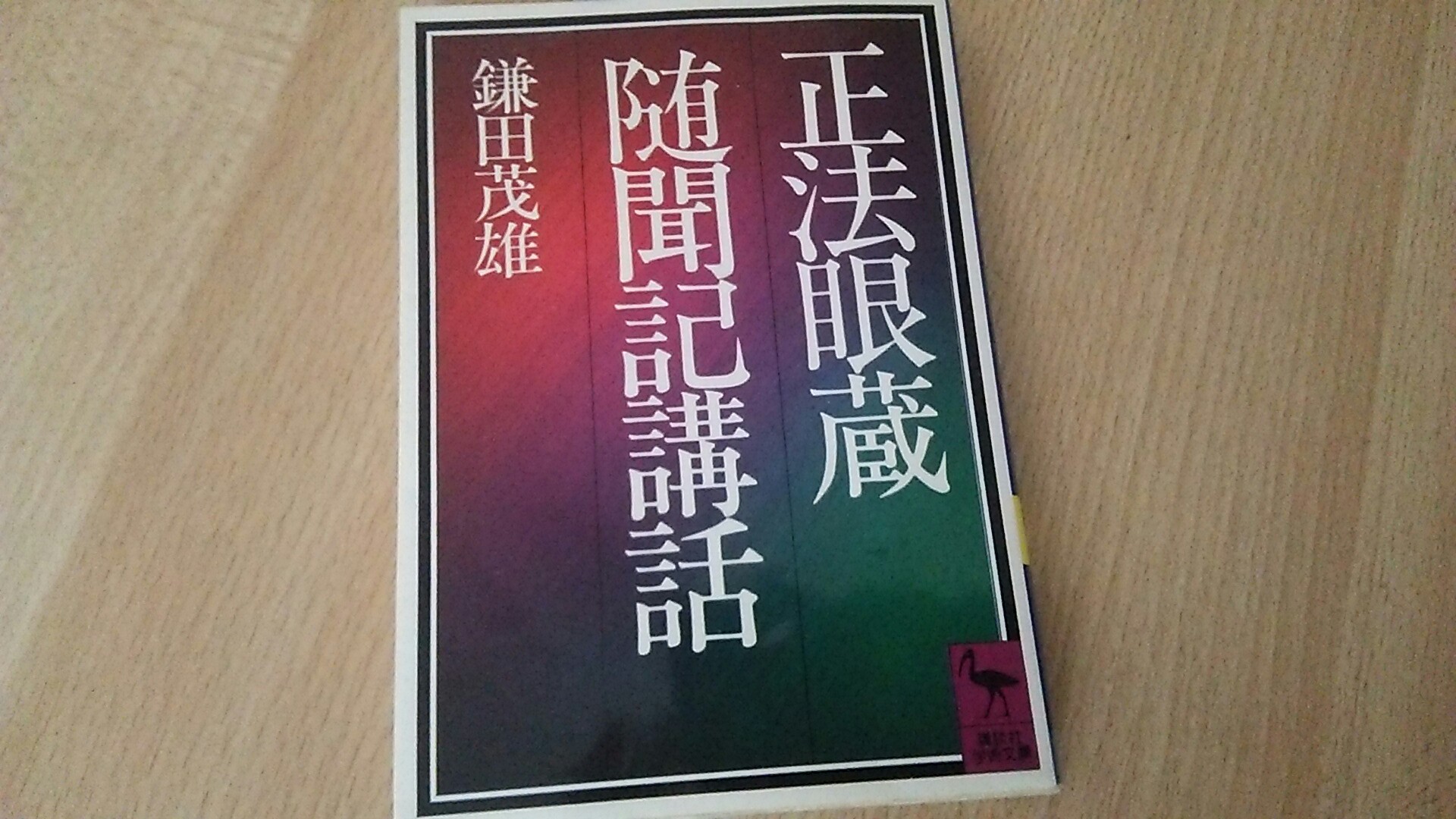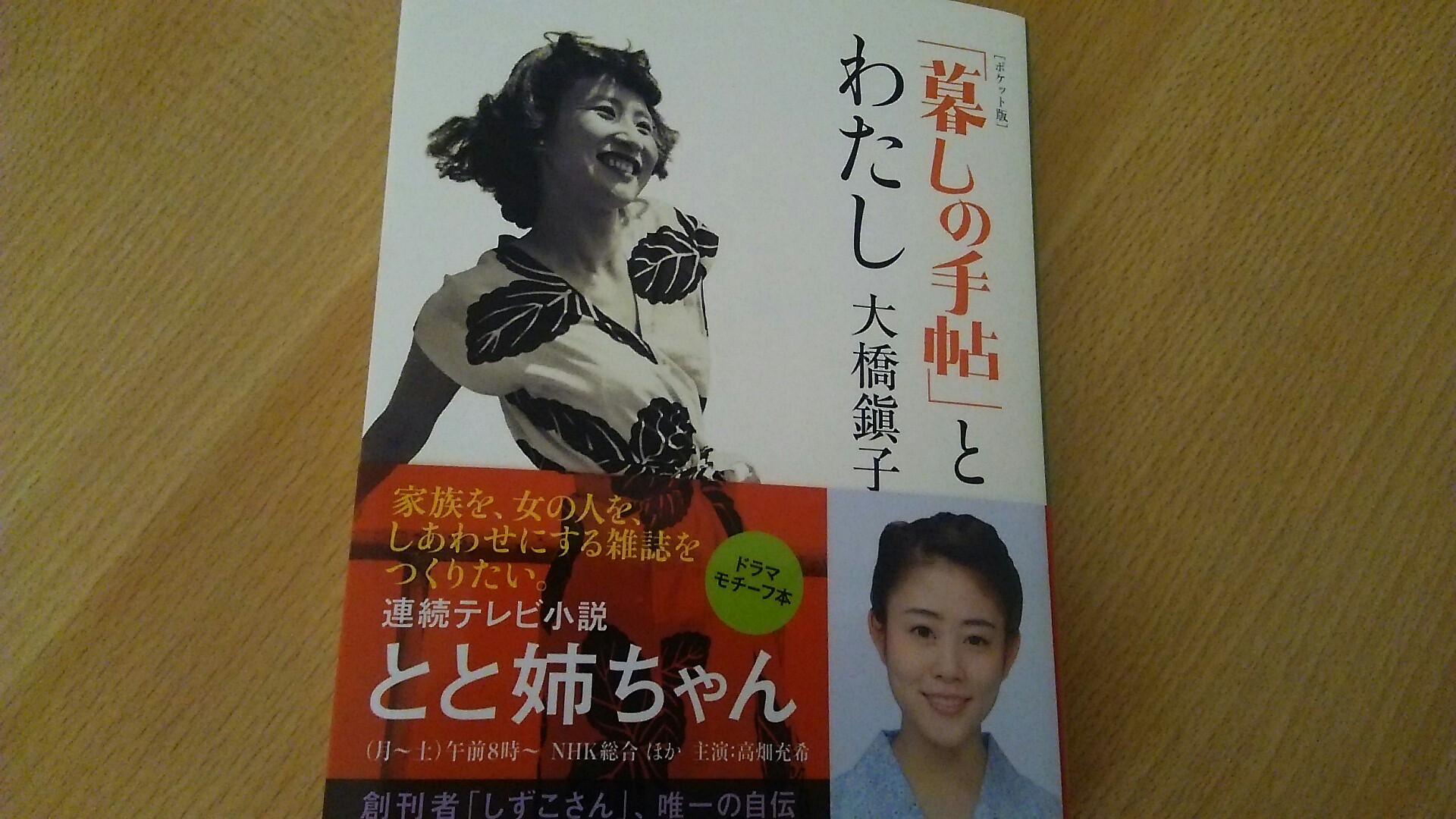ジャーナリストの池上彰さん、学者の外山滋比古さんの本を読むと、「辞書を読む」習慣があることがわかります。辞書を読む、その効果はどうでしょうか。池上彰さんや外山滋比古さんの辞書の読み方を知って、語彙力をアップしましょう。
辞書を読む その効果は? 池上彰さんや外山滋比古さんの辞書の読み方を知って語彙力を増やす
中3国語の授業で辞書を読むという内容の論説文をやったとき、「辞書なんか読んでもおもしろくないじゃろ」と皆が口々に言うので「そんな皆さんにおすすめなのがこちら!」とテレビショッピングの人みたいに紹介した辞書がこちら⬇️ pic.twitter.com/W4srN09jRr
— 紅葉 (@Herbst_Ahorn) November 5, 2024
池上彰さん
「重い辞書を枕元に置いた父は、少しずつページを繰っては、読み進んでいました。小説ならともかく、辞書を読むなんて。その旺盛な知識欲に私は圧倒されました」。
フリージャーナリストの池上彰さんは、著書「学び続ける力」(講談社現代新書)で、こう書いています。
米寿を過ぎて寝たきりの生活になったお父様が、岩波書店の「広辞苑」第四版が発売されたのを知って、池上さんに、購入するように頼み、亡くなるまで読み続けたのだそうです。
「『広辞苑は』は、父の形見になりました。『広辞苑』は、いま第六版が出ていますが、私には第四版が宝物です」と池上さんはその思い出を振り返っています。
Audible (オーディブル) – 本を聴くAmazonのサービス
外山滋比古さん
学者の外山滋比古さんも、著書「知的生活習慣」(ちくま新書)の中で、「辞書を読む」として、英和辞書だけでなく、「新明解国語辞典」を机上に置いて、毎日のように、引いて読んだことを書いています。
「ことばが問題になると、私はすぐ『新明解』、それでわからぬとき、要領を得ないときは、『大辞林』を見る。一般的には、『広辞苑』のほうが人気が高いようだが、私は年来、『大辞林』を信用、愛用している」と外山さんは同著で書いています。
知識欲は、外山さんにも共通しています。
辞書を読む その効果は?
辞書を読むことの効果としては、日本語の語彙力が大きくアップすることでしょう。知らなかった語彙に出会えば、使える語彙が増えます。また、知っている語彙でも、違う意味を知れば、その語彙に対する理解がさらに深まります。日本語が豊かになっていきます。
日本人にとっては、日本語は母国語なんだ、という意識が強まります。
語彙の成り立ちを知れば、日本の歴史や文化にも興味が広がっていくでしょう。
あわせて読みたい
朝日新聞デジタル 紙面との違いは? レビューでメリット、デメリットを比較
大人になって、漢字が書けない、思い出せない こんな時の対策は? 漢字練習方法を解説【情報力アップ】
字手紙とは? 字手紙の書き方は? 年賀状でも応用しましょう
【朝日新聞デジタル】便利な機能で効率よく情報収集!![]()
朝日新聞デジタル「就活割」を活用して内定をGET
![]()
辞書はどんな風に読むか
「国語辞典は使っていません」という人に「スマホの辞書アプリが便利ですよ」とお勧めするのですが、なかなかイメージしてもらいにくいです。そこで、こんなチラシを作り、お会いする人に配ったりしています(迷惑)。辞書好きの皆さま、もしよろしければ印刷して、配布にご協力くださいませんか。 pic.twitter.com/ichBSGWAYg
— 飯間浩明 (@IIMA_Hiroaki) November 19, 2024
では、辞書をどんなふうに読んだらいいでしょうか。
まず、気軽に辞書を手にすることでしょう。池上さんのお父様のように、1ページごとに読み進めるのは、次に、どんな日本語に出会うかワクワク感があります。一つの言葉に対する興味が増します。いろいろな解釈、言葉の使い方に、新たな発見、驚きがあることでしょう。
外山さんのように、言葉に出会って、疑問などを感じたら、辞書にあたって調べるのはオーソドックスな辞書の使い方です。一つの言葉を多くの辞書で引いてみると、一つの言葉に対する理解が深まります。
机上に辞書を置いておけば、すぐに調べることができます。時間があったら、パラパラとページをめくって、手あたり次第、読んでみるといいでしょう。辞書への愛着も増しますから、日本語の語彙力も深まります。
福沢諭吉の功績
網野善彦著「歴史を考えるヒント(新潮文庫)」読了
古代〜中世日本について明るく無いのでとても参考になり興味深かった(付箋を更に半分に切って貼りまくる事態に…)Libertyを福沢諭吉が「自由」と翻訳したのは有名だけど、その言葉自体は我儘、放蕩の意味合いで存在してたとは知らなかった pic.twitter.com/O5YUal3VZu
— めっつ (@velvetmonk_pma) September 14, 2023
「演説」「西洋」「自由」などの言葉は今や、すっかり、現代用語として定着していますが、江戸時代までなかったものです。慶應義塾大学を創設した啓蒙思想家の福沢諭吉(1835年-1901年、慶應義塾大学創設者)が、新しい西洋文化の概念を日本語の訳語に置き換え、その地道な作業の結果、生まれたものです。日本文化を変革した偉業と言えるでしょう。
あわせて読みたい
福沢諭吉が翻訳した言葉は? その功績を知る 西洋文化の概念を日本語に翻訳
Audible (オーディブル) – 本を聴くAmazonのサービス
まとめ
【#辞書のおしごと】
新しくフォローしてくださった皆さんに、当編集室の仕事をご紹介。こちらは辞書を中心とする編集部で、日夜、新刊の企画を練ったり、改訂の作業を進めています。辞書にも大小があり、いちばん大きな辞書は『#日本国語大辞典』、通称 #日国。いま第三版の改訂を進めています。 pic.twitter.com/FkHdboYqXT
— 小学館 辞書編集室 (@shogakukanjisho) November 23, 2024
辞書を1ページ、1ページを繰って、あるいは、好きな個所を開いて目に飛び込んできた語彙を読み込む。そして、一語一語の日本語の意味をかみしめる。辞書を読むのが楽しくなるはずです。
あわせて読みたい
新聞スクラップのやり方 何度も繰り返して読んで、情報力アップ 7つのポイントに注目! 【情報力アップ】
新聞電子版のスクラップのやり方 紙面ビューアーで簡単で効率的に
新聞記事の要約の仕方は? 見出しを活用した実例を7つのポイントで解説
池上彰さんのスクラップ手法に学ぶ 新聞記事を「寝かせる」 重要な情報を見つけるためのスクラップの極意 【情報力アップ】
情報カードの使い方は? 発想が発想を呼ぶ その方法を7つのポイントで解説!
立って仕事をするメリットは? 集中力アップで効果を上げた人物は? ヘミングウェイの仕事現場も見る
読書の効果を実感! 本の読み方のコツは? 本の読み方を7つのポイントで解説
大人になって、漢字が書けない、思い出せない こんな時の対策は? 漢字練習方法を解説【情報力アップ】
メモ帳「ジョッター」の使い方とは? 一番のおすすめを5つのポイントで解説 【情報力アップ】
クリアホルダーの使い方 情報収集の上手い人がやっている方法
あわせて読みたい
朝日新聞デジタル 紙面との違いは? レビューでメリット、デメリットを比較
就活におすすめの新聞は、どこの新聞? いつから読むべきか?
就活のための時事問題対策 新聞のニュース記事で勉強 読まないと不利にも