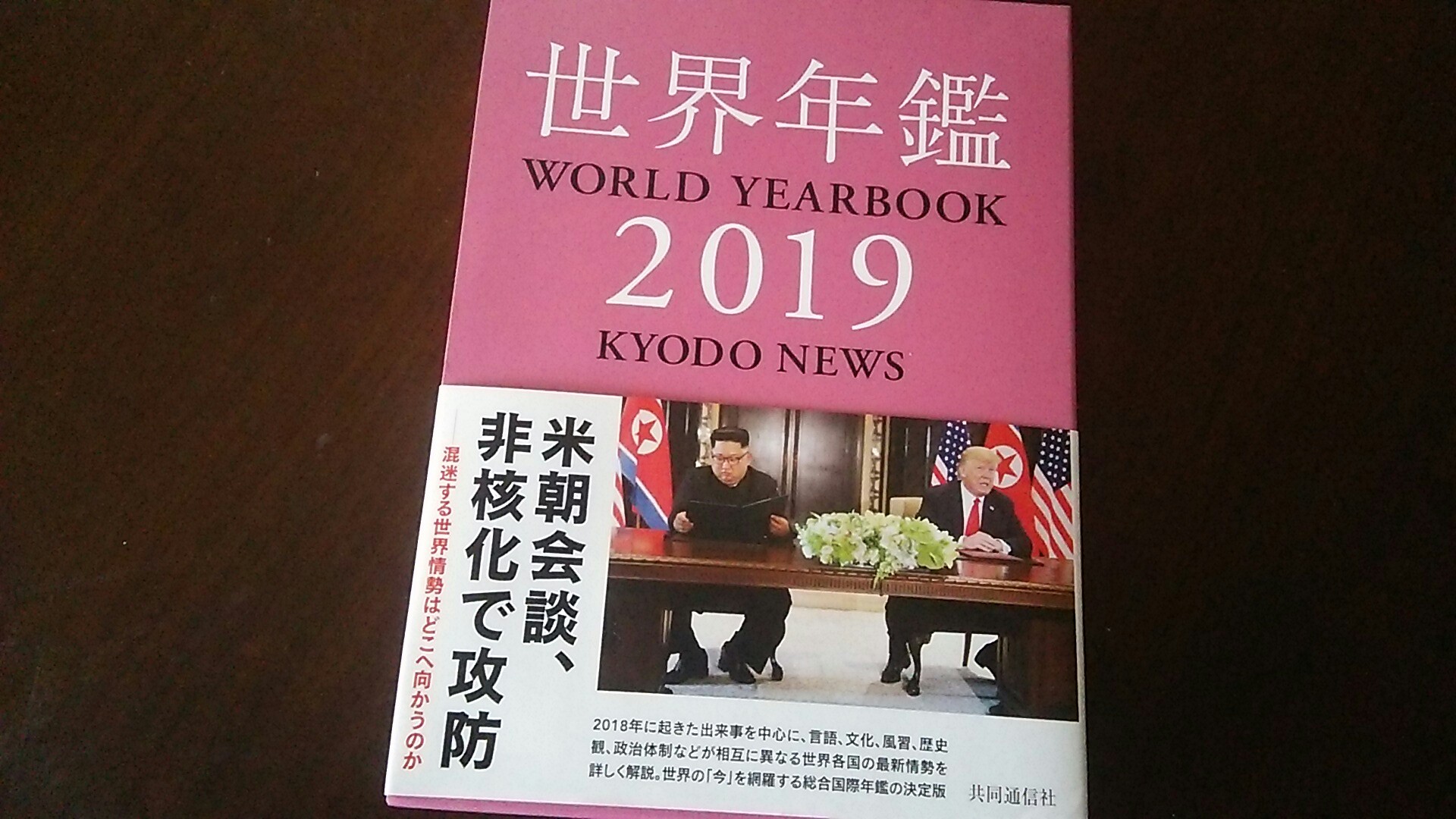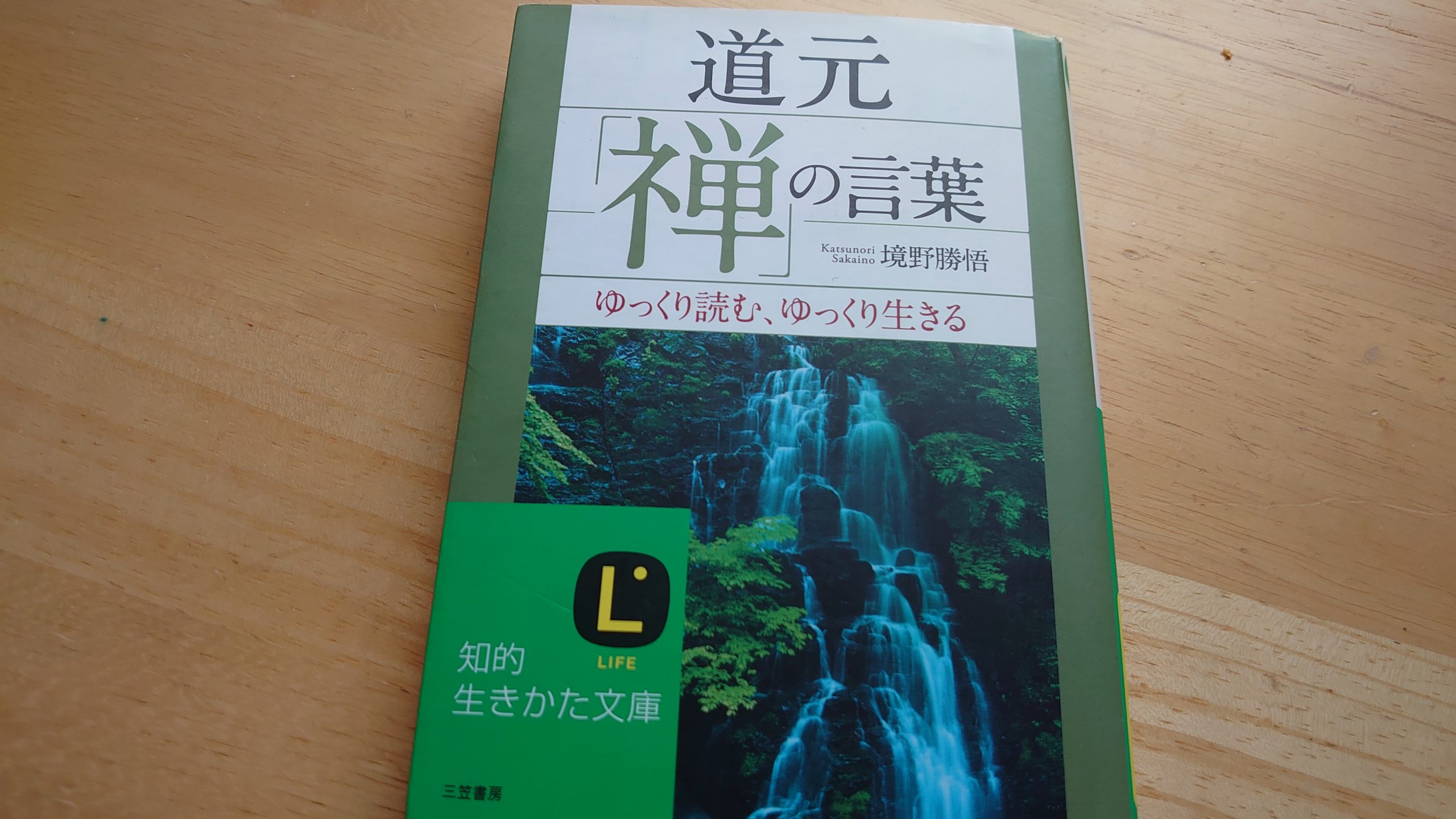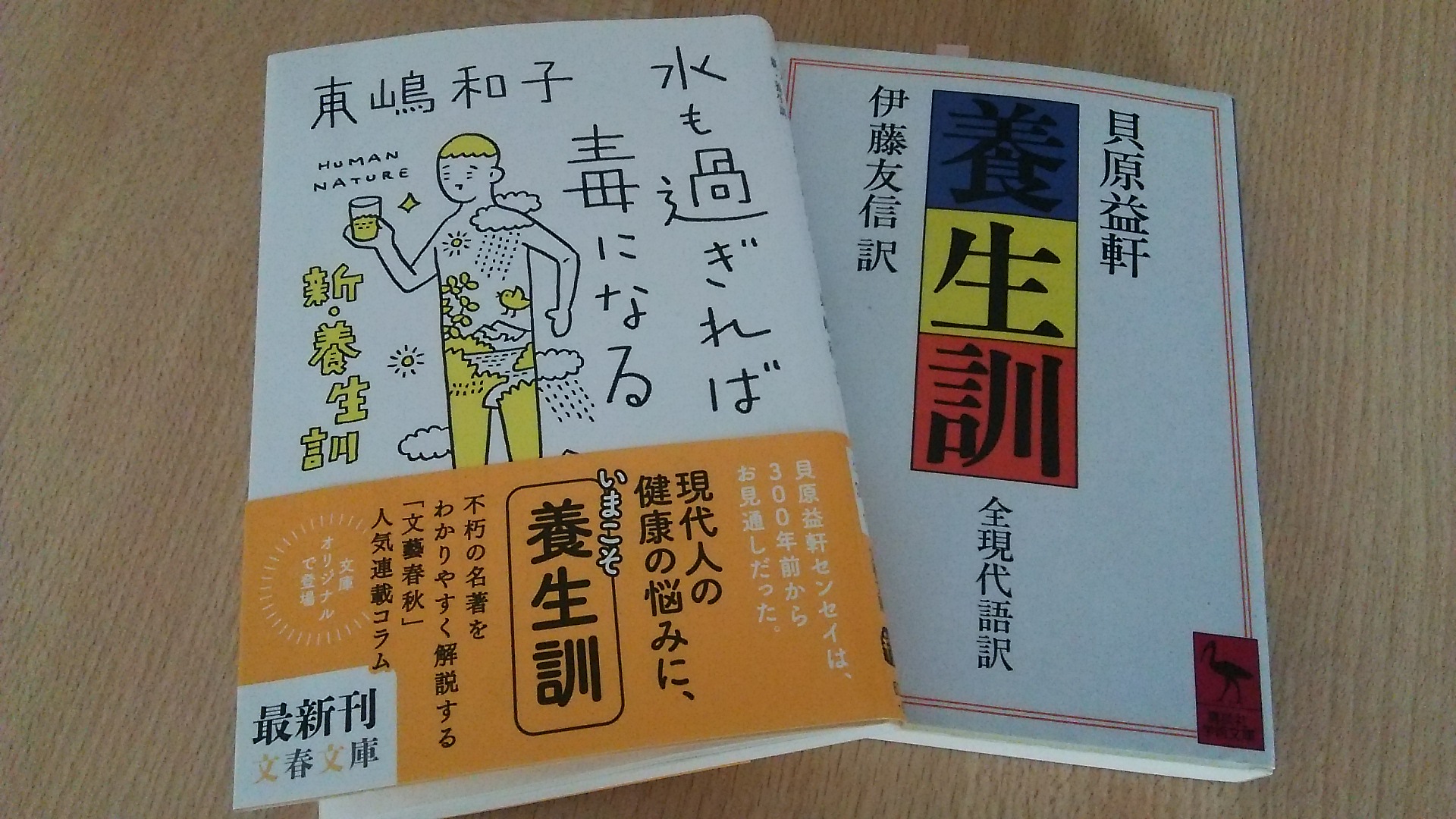「無功徳(むくどく)」という禅語は、大切にしたい生き方を示してくれる言葉の一つです。無功徳とは、どんな意味の禅語でしょうか。また、無功徳の出典は達磨大師でしょうか。建功寺(神奈川県)住職の枡野俊明さん、境野勝悟さん、そして、全生庵(東京都)住職の平井正修さんの著書から、「無功徳」についての解釈をまとめてみました。無功徳を座右の銘にしましょう。
無功徳とは? どんな意味の禅語? 無功徳の出典は達磨大師?
#一日一禅 溜め込んでしまい一日二禅でも追いつけません。すみません。
①無功徳/碧巌録より
役に立つ事をした。だから良い事が返って来るだろう。
…じゃない。
果報を期待しない。
行いはそれで完了。正しい事をする、それだけ。
(でも悪い事をしたら、たぶん悪い事が返って来る)
スレッド続く pic.twitter.com/pWMvchn76y— 正眼短大/禅の学校 (@shogentandai) June 17, 2024
3人の方とも、まず、禅語の「無功徳」が達磨大師の言葉であることを指摘しています。
枡野さんの著書「おだやかに、シンプルに生きる」によると、昔、梁(りょう)という国に武帝がおり、その武帝が、自分は仏教の興隆のためにお寺を自費で建て、一生懸命、写経もしてきたといいます。そのうえで、武帝は「いったいどのような功徳が私には与えられるのでしょうか?」と達磨大師に尋ねました。
これに対して、達磨大師は一言、「無功徳」と答えました。枡野さんは、「要するに、禅的な行為というものは、いっさいの果報を求めないことが基本なのです」と解説しています。
深く考えさせられる言葉です。
おだやかに、シンプルに生きる (PHP文庫) [ 枡野俊明 ]
境野さんも著書「心がスーッと晴れる一日禅語」の中で、「たとえ、友だちにいいことをしたり、いいものをあげても、あれもした、これもしたと、恩に着せたり、鼻にかけたり、お礼をいわれたりしようとしない。まず、人にものをあげる余裕のあることに感謝せよ・・・と。人に親切にしても、ご利益は求めない」として、「見返りを期待しない」ことが大切であることを強調しています。
【中古】 心がスーッと晴れる一日禅語 「あらゆる迷い」を解決するヒント 知的生きかた文庫/境野勝悟【著】
また、平井さんも著書「男の禅語」の中で、「『したことは報われるはずだ』と考えているから、苦しみがはじまるのです。・・・見返りを求める心から解放され、『自分がしたことは、やっただけで終わり』となるのなら、余分な負担がなくなり、常に心を軽くして生きられるに違いありません」として、境野さんと同様、「見返りを期待しない『潔さ』」の重要性を説いています。
見返りを求めない。そうすることで、穏やかな心を保つ。そんな生き方の大切さがわかります。なかなか実践が難しいですが、常に心に留めておきたい禅の言葉です。
【中古】 男の禅語 知的生きかた文庫/平井正修(著者)
男の禅語 「生き方の軸」はどこにあるのか【電子書籍】[ 平井正修 ]
無功徳のまとめ
《無功徳》
功徳とは善い行いに対する報酬のようなもの。しかし功徳を得るために下心をもって善い行いをしても、功徳は遠ざかってしまいます。善行はあなたの利益のために行うものではありません。見返りを期待せず無心で行うことが大切なのです。善い行いに出会えた縁にに感謝を— 仏の教えwords of wisdom (@namutyan) October 3, 2024
「『努力をすれば必ず報われる』という言い方があります。その通りだと思います。ただし、『報われる』というのは、成果が出るという意味ではなく、その本当の意味は、自分自身の人生が豊かになるということです。人生とは、淡々とした小さな努力によって善(よ)きものになっていくのです」
枡野さんは、こう解釈しています。
小さくても日々、努力を積み重ねる。そして、自分の人生を自分の理想に近づけ、豊かなものにしていく。「無功徳」は、「努力」という言葉の意味をも問い直すものになります。
あわせて読みたい
而今(にこん) 今、この瞬間を大切に生きる 禅の言葉をかみしめて
禅語の非思量の意味とは? 怒らない、怒りを抑える方法を禅の本で学ぶ【心に響く禅語】
自灯明とは? 読み方や意味をわかりやすく解説! 瀬戸内寂聴さんらの解釈にも注目。
執着しない方法や、小欲知足、無分別の意味を知って生きる 「ためない練習」(名取芳彦著)の感想から
道元禅師の名言「欠気一息あるべし」から、座禅のありかたを学ぶ
放下着(ほうげじゃく)とは、どんな意味の禅語? 枡野俊明さんや平井正修さんの解釈 【心に響く禅語】
リーダーが座右の銘とすべき禅語は? 「リーダーの禅語」(枡野俊明著)から学ぶ
執着しない方法や、小欲知足、無分別の意味を知って生きる 「ためない練習」(名取芳彦著)の感想から立禅の簡単なやり方や適切な時間は? 姿勢、呼吸、心を整える立禅の効果を実感し!
日日是好日の読み方や意味は? この禅語、日日是好日を座右の銘にしよう
あわせて読みたい
朝日新聞デジタル 紙面との違いは? レビューでメリット、デメリットを比較
就活におすすめの新聞は、どこの新聞? いつから読むべきか?
就活のための時事問題対策 新聞のニュース記事で勉強 読まないと不利にも