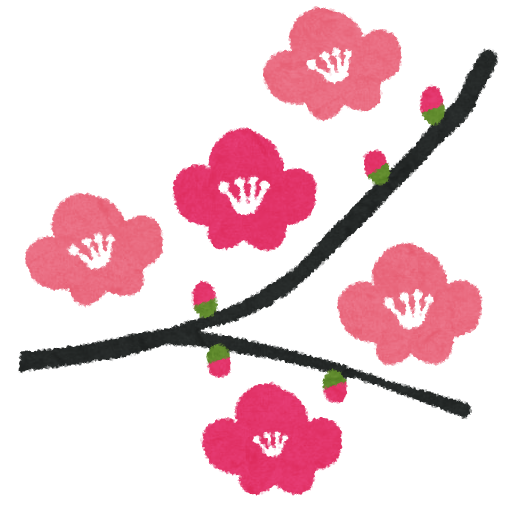1月7日の朝、七草粥を食べる風習があります。七草粥を食べる理由、意味とはどんなものでしょうか。また、七草粥の歴史や由来はどうなっているのでしょうか。七草の種類と効能を含めて、七草粥についてまとめました。お正月の後にやって来る食文化を大切にしたいものです。
七草粥を食べる理由、意味とは?
七草粥🌿の日だけど、昨日の夕方、スーパーに七草買いに寄ったら、いつのや?ってくらい、しなびたのしか売ってなかったので、その💰で🍓買いました😂
お家にあった大根と大根葉で一草粥🌿😆
代わりに、七色おもち添えといたw
金沢の佃煮🐟を添えて🌟
無病息災を祈って🙏#人日の節句 pic.twitter.com/Ch0v5bd8a2— ことりす🍂🐿️ (@cotoris_3939) January 7, 2024
お正月の豪華なご馳走で胃が疲れ気味になりますが、七草粥は、そんな胃を助けてくれる優しい味となります。
そのうえで、松の内の最後に、
無病息災
長寿
健康維持
立身出世
などを願って食べるものです。
新年を迎えたばかりで、祈りも強まりそうです。ちょうど、受験の前の時期にもあたりますから、合格祈願する人も多いはずです。
七草粥の歴史や由来は?
年末年始は風邪をひいたので、無病息災を願って朝ごはんは七草粥。何気に初めて作ったかも…。 pic.twitter.com/9gdKpSyLj9
— 村井美樹 (@mikimurai) January 7, 2019
七草粥の歴史や由来を調べると、七草粥は、古代中国から日本に伝えられ、奈良、平安、そして、江戸時代を経て、出来上がった風習であることがわかります。
七草粥は、時代を経て引き継がれてきた風習です。
中国では
中国では前漢時代(紀元前208年から206年)、新年の運勢を占う儀式が始まりました。新年を迎えて、
元日は鶏
2日は犬
3日は猪
などについてそれぞれ占い、1月7日は、人の日として、人について占いました。
長年、この占いは続きましたが、唐時代(618年から907年)になると、この1月7日に、7種類の野菜を煮込んだ汁物を食べて、無病息災、長寿、健康維持を願うようになりました。また、この日には、官吏の昇進が発表されたことから、立身出世を願うものともなりました。
7種類の野菜から、この汁物は、「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」と呼ばれました。七草粥の原形とも言えるものです。
日本に入って
日本では奈良時代、若い野菜を摘んで正月に食べる「若菜摘み」の食文化がありました。この時期、中国から、「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」の風習が日本に入り、時代が平安へと移り変わる中で、「若菜摘み」と「七種菜羹」の風習がミックスされて、七草粥が誕生することになりました。
さらに、江戸時代になって、幕府が、1月7日を、「人日の日」として、五つの節句の一つに定めたことから、七草粥がこの日に食べられることになり、大きな風習として定着しました。
日本が中国から食文化でも大きな影響を受けたこと、中国の食文化が日本の食文化と結びついてきたことがわかります。
春の七草 10袋 こだま食品 フリーズドライ 国産
Audible (オーディブル) – 本を聴くAmazonのサービス
七草の種類と効能は?
せりなずな
ごぎょうはこべらほとけのざ
すずなすずしろ…
と唱えつつ、
八ヶ岳の濃い七草を
いただきます。あをあをと春七草の売れのこり 高野素十
七草粥欠けたる草の何何ぞ 鷹羽狩行
七草の根のほそほそと混み合へり
正木ゆう子#七草粥 #俳句 pic.twitter.com/zrttRvZ5Ym— 徳井いつこ (@tea_itsuko) January 7, 2024
七草粥に入れるのは、春の七草と呼ばれるものです。ちょっと、小さい頃を少し思い出してみましょう。
セリ
ナズナ
ゴギョウ
ハコベラ
ホトケノザ
スズナ
スズシロ
こう言ってよく春の七草を覚えた人も多いのではないのでしょうか。まさに、これらの七草が、七草粥の「主役」になります。
そんな七草粥ですから、七草のひとつひとつに、さまざまな効果、効能があります。以下のようなものです。
セリ
独特の香りがあり、
ビタミンA
ビタミンC
カルシウム
リン
カリウム
を含みます。
食欲増進
解熱
整腸
利尿
高血圧防止
などの効果、効能があります。
また、密集して生えることから、競り勝つとして、出世などの幸運を願うものにもなっています。
ナズナ
ぺんぺん草とも言われます。江戸時代によく食べられた野菜で、
解毒
解熱
止血
利尿
むくみ防止
高血圧防止
などの効能があります。
ゴギョウ
母子草とも言われます。
痰や咳の防止・緩和
解熱
風邪予防、
むくみ防止
などの効能があります。
ハコベラ
ハコベとも言われ、中国でも薬草としてよく知られていました。
ビタミンC
カルシウム
カリウム
フラボノイド
などが含まれ、
腹痛防止・緩和
胃炎防止
止血
利尿
などの効能があります。
ホトケノザ
食欲増進
整腸
高血圧防止
などの効能があります。
スズナ
カブ(蕪)を指します。ビタミンが豊富で、
整腸
便秘防止
骨粗鬆症防止
がん予防
などの効用があります。
スズシロ
大根を指します。
ビタミンA
ビタミンC
フラボノイド
ジアスターゼ
などを含み、
消化促進
二日酔い解消
頭痛緩和
便秘解消
などの効能があります。
身近にある野菜から、栄養を摂り、多くの病気を避ける。春の七草には、さまざまな効能があり、先人たちの知恵が詰まっています。
【ネコポス送料無料】フリーズドライ春の七草2.5g×1P(2人前)×10袋 野菜代わりに
七草粥のまとめ
◆七草粥/由来◆
1月7日の人日(じんじつ)の節句の行事食。
その日の朝に「春の七草」が入ったおかゆを食べると、1年間を無病息災で過ごせるとされています。
<人日とは、江戸幕府の公的行事・祝日としての五節句の一つ。人日、上巳、端午、七夕、重陽>
明治政府は江戸の全てを否定し、廃止今に至る pic.twitter.com/Y2ldZoCW00— kazu (@kazu409366471) January 6, 2021
七草粥を食べる風習は減ってきていますが、時には、日本の伝統食に目を向け、先人たちの知恵を感じたいものです。もし、春の七草がなければ、ネギやミツバなど身近にある野菜を使って七草粥を作ることもできます。
食材として使う野菜の効果、効能を調べれば、日頃、食べている野菜に対する感謝の気持ちが生まれてきます。「MY七草粥」の出来上がりです。スーパーで売っている「七草粥セット」を購入してもいいでしょう。
あわせて読みたい
年越しそばの歴史は? いつから始まった? なぜ、年越しそばを食べるの? 由来や歴史、特徴などを解説
正月飾りの期間2024年はいつからいつまで飾る? 意味や由来、捨て方も含めて
日枝神社(赤坂)への初詣2025年の混雑予想は? 神猿をなでる、ご利益は?
川崎大師への初詣2024年の混雑状況やおすすめの参拝時間は? 駐車場や屋台情報も含めて
明治神宮への初詣2025年は、どのくらいの人数で混雑? おすすめの参拝の時間帯は?
自灯明とは? 読み方や意味をわかりやすく解説! 瀬戸内寂聴さんらの解釈にも注目。
年末年始休み2024年-2025年はいつからいつまで? 官公庁、銀行、企業、サービス業の業種別に
あわせて読みたい
朝日新聞デジタル 紙面との違いは? レビューでメリット、デメリットを比較
就活におすすめの新聞は、どこの新聞? いつから読むべきか?
就活のための時事問題対策 新聞のニュース記事で勉強 読まないと不利にも