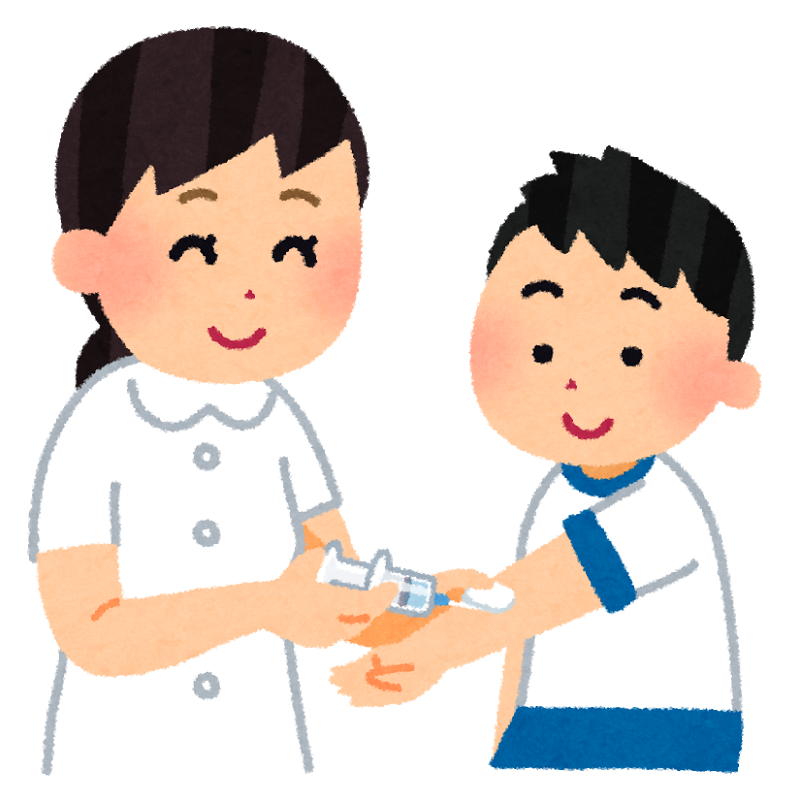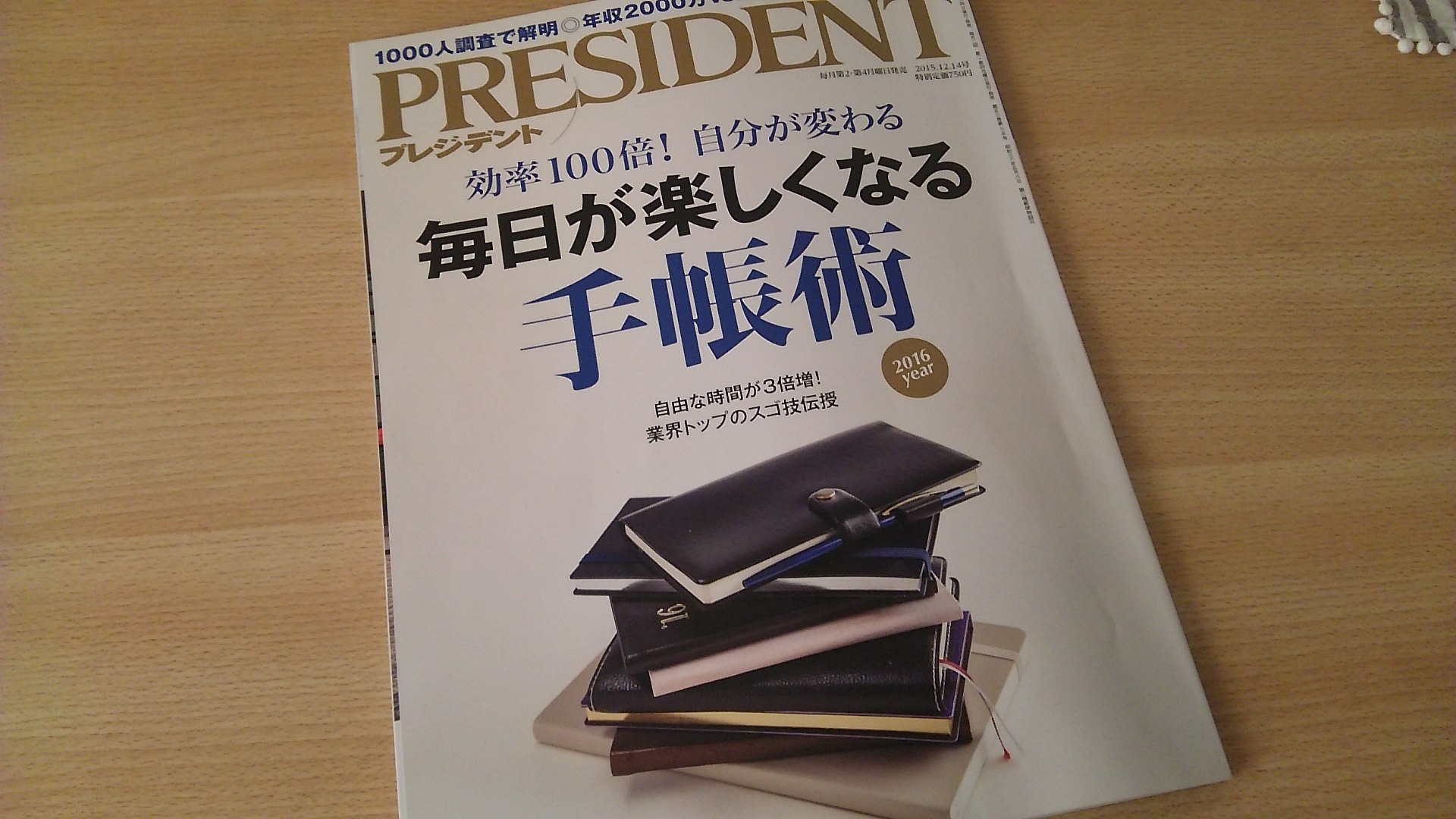桃の節句(ひな祭り)と言えば、桜餅、端午の節句(子供の日=5月5日)と言えば、柏餅が代表的な食べ物でしょう。端午の節句に、柏餅を食べる意味や由来は何でしょうか。また、柏餅はいつから食べるようになった行事食なのでしょうか。柏餅の葉っぱは食べるかどうかも含めて、柏餅についてまとめました。
端午の節句に柏餅を食べる意味や由来は?
二日遅れだけど、こどもの日の柏餅を妻が作ってくれました🎏 pic.twitter.com/pbG466D5On
— エンジニアとんちん🐟家族で海外生き残り (@0125Tonchin) May 7, 2023
端午の節句に柏餅を食べる意味は?
柏餅と言われるように、柏の葉に意味があります。柏は、神聖な木と昔から尊ばれてきました。そして、新芽が出て育つまで、古い葉が落ちません。
こんな特性から、柏の葉は延々と生命を逞しくつなぐものとして考えられ、
「子孫繁栄」
「一家安泰」
を願う縁起物の食べ物として親しまれるようになりました。
端午の節句 子供の日 子供の日 内祝 お祝 ランキング プレゼント スイーツ ギフトセット 誕生日 ありがとう 和菓子 /送料込 かしわ餅(柏餅)8個・ちまき5本セット
端午の節句に柏餅を食べる由来は?
名前の由来はもちろん、柏の葉を使ったことが一番の理由ですが、柏手(かしわで)にも由来しています。
柏手は音を出して両手を合わせるものですが、神への感謝や喜びを表現するために行います。柏餅は、こんな感謝などを込めた食べ物にもなっています。
端午の節句に柏餅はいつから食べるようになった?
こんにちは😊東照です!
5月4日、5日とアゼリアの東広場にて柏餅の催事を行います♪
柏餅、湘南ゴールドどら焼き🍊など沢山ご用意しておまちしております💕#企業公式相互フォロー#柏餅 #湘南ゴールド#催事 #川崎 pic.twitter.com/uBPtUHB7yQ— 東照アゼリア店(公式) (@toteru_azalea) April 20, 2024
端午の節句に、柏餅が食べられるようになったのは江戸時代中期です。最初は江戸で食べられましたが、参勤交代で全国の諸大名がお国と江戸を往復する中で、端午の節句に柏餅を食べる習慣が全国に広がりました。
参勤交代は、食文化を全国に普及させる役割も担いました。
冷凍 和菓子 ミニ 柏葉もち ( かしわ餅 ) 20個 解凍後そのままお召し上がり頂けます。( 柏の葉は食べれません )